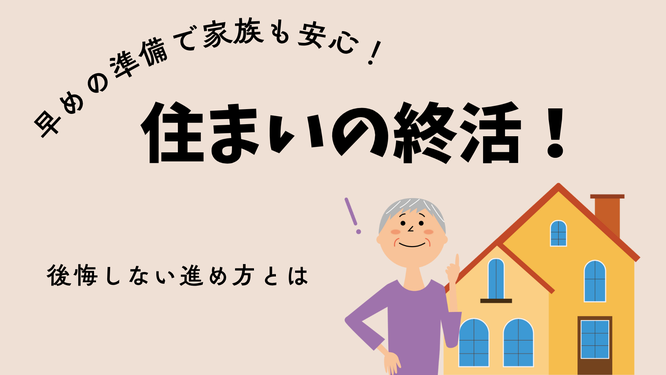
終活は自分らしい人生の最期を迎えるための準備として注目されています。
「住まい」の終活は、自分が安心して暮らせる場所を確保するとともに、家族・相続人の負担を減らす重要な選択です。
本記事では、なぜ住まいの終活が必要なのか、その主な方法、実践手順、注意点など具体的にご紹介します。
住まいの終活が必要な理由
人生の終わりに備え、預貯金や保険の見直しを行う人は多くいますが、「住まい」についての終活は十分に行われていないことも多いものです。
大切な家族が後で困らないためにも、住まいの整理や相続の準備はとても重要です。
住まいの終活を行うことで、どのような負担軽減や問題防止につながるのか、詳しく見ていきましょう。
子どもや家族への負担軽減
住まいの終活を進める最大のメリットは、子どもや家族に対する相続や管理の負担を大幅に軽減できる点にあります。
ご自身が亡くなった後、「実家や持ち家をどうしたらよいのか」「相続分配をどうすればいいのか」といった問題は、遺された家族の大きな悩みになりがちです。
また、家の管理や売却の手続きは、時間も労力もかかります。
生前に住まいに関する意思表示や整理を行っておくことで、家族が迷ったり争ったりするリスクを減らせるだけでなく、管理の負担からも家族を守ることができます。
不動産の処分・整理問題
終活の一環として住まいを整えることは、空き家や相続の複雑化などのリスクも防げます。
自分が住まなくなった後の不動産を何もせずに放置しておくと、空き家問題が生じやすく、建物の傷みや近隣への迷惑、さらには税負担も増します。
生前に相続の方針を決め、必要な手続きも進めておくことで、社会問題への発展を防ぐことができます。
住まいの終活の主な方法
預貯金や保険の準備に加え、住まいについても早めに行動することで将来の安心と家族の負担軽減につながります。ここでは、具体的な住まいの終活方法をご紹介します。
賃貸物件や施設への住み替え
暮らしや健康状態が変化しても快適に過ごせるよう、生活環境に合った住まいへの住み替えを検討するのも一つの方法です。
例えば、バリアフリー仕様の平屋住宅やエレベーター付きマンション、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)などが候補に挙がるでしょう。
サ高住はバリアフリーで安否確認や生活相談サービスもあり、高齢の方でも安心して暮らせます。
こうした住まいに移ることで、家のメンテナンスや庭の管理、掃除などの負担が大幅に減り、心身の負担を軽減できます。
元気なうちから情報収集や見学、家族との相談を進めておくと、もしもの時にもスムーズです。
清算型遺贈の活用
精算型遺贈とは、不動産などの財産を現金に換えててから、相続人に引き渡す相続方法のことです。
この方法を使うと、相続人に次のようなメリットがあります。
- 遠方に住んでいても手続きに関わらずに済む
- 不動産の売却に手間をかけずに済む
- 換金されたお金を受け取るだけで済む
さらに、第三者である遺言執行者を指定しておけば、手続きの一切をその人に任せることができるため、相続人の負担はほとんどありません。
家族への生前贈与
持ち家や不動産を生前に家族へ贈与することで、相続時のもめごとを予防できます。
生前贈与は、贈与税が発生する場合もありますが、住宅取得資金贈与の特例など、条件によっては非課税枠を活用することも可能です。
生前贈与を行う際は、贈与を受けた家族の住まい確保や税金の確認など、事前に十分な準備をしておくとより安心です。
ただし、生前贈与しない方が節税効果が高いケースもあるため、専門家に相談する方がよいでしょう。
住まいの終活の進め方
住まいの終活を進める際は、早めに将来に備えておくことが大切です。焦らずに一つひとつ段階的に取り組むことで、ご自身の希望が反映され、家族も安心できる状況を作ることができます。
所有不動産のリストアップ
まずは、自宅や所有している土地、借地権などを正確に把握しましょう。
不動産ごとの場所・利用状況・面積などをリスト化すると管理がしやすくなります。
また、各不動産の登記事項証明書や契約書といった重要書類の保管場所を家族が分かるようにしておくことが大切です。
どの不動産を自分がどのように扱いたいのか、整理しておくとスムーズな相続や売却に役立ちます。
家族としっかり話し合う
思いをカタチにするためには、家族と早めに話し合いを持つのがポイントです。
自分の希望や想い、住まいをどうしたいかを率直に伝えることで、家族も準備ができます。
後からのトラブルを防止するためにも、話し合いの記録やメモを残しておくとよいかもしれません。
また、家の中や思い出の品の写真を撮っておくのもおすすめです。
写真があれば思い出をふり返りやすく、長年住んだ家がなくなると寂しさもやわらぐでしょう。
相続税や登記手続きの確認
不動産を相続する際は、相続税の試算や不動産登記の手続きについても事前に確認が必要です。
法制度も年々変化しているため、最新情報を押さえておきましょう。
また、知識が難しい部分や判断に迷う場合は、不動産会社・税理士・弁護士・行政書士といった専門家に相談するのがおすすめです。
専門家のサポートを受けることで、ご自身とご家族にとって最適な道筋を描くことができます。
住まいの終活を考える上での注意点
住まいの終活を進める際は、専門的なサポートが大切です。ここでは、失敗しない終活のために意識しておきたいポイントを解説します。
体力や判断力があるうちに準備する
住まいの終活は体力や判断力が十分にある60代や70代から始めるのが理想です。
年齢を重ねると、体調面だけでなく判断力や記憶力の低下もあり、重要な意思決定や細かい手続きを進めるのが難しくなりがちです。
たとえば、不動産売却や贈与、相続の準備には多くの書類確認や相談事が発生します。
そのため、元気なうちに方針を決め、余裕をもって進めることが、ご自身にとっても家族にとっても安心につながります。
相談先や利用できるサービスを知っておく
住まいの終活には多方面の専門家のサポートが必要になります。
たとえば、税金や節税については「税理士」、不動産の処分や売却は「不動産会社」、遺言書の作成や必要書類の確認は「行政書士」と、相談するべき窓口が分かれています。
しかし、それぞれ個別に相談を重ねると、手間もコストも大きくなりやすい点に注意が必要です。
「何から手を付ければよいか分からない」という場合は、まず相続や住まいの終活全般に詳しい窓口に相談するとよいでしょう。
当社では税理士・弁護士・行政書士・不動産会社と連携し、相続・売却・税金・遺言など幅広い分野を一括で相談・解決できるため、安心して手続きを進められます。
清算型遺贈を選択して住み替えした事例
浅井廣次さん(仮名・70代)は、長年住み慣れた一戸建てを売却し、駅近のマンションへ住み替える決意をされました。
きっかけは、娘さんとの会話。
「仕事が忙しくて、実家の売却まで手が回らない」と話す娘さんの言葉が心に残ったといいます。
また、アパートでは不安があるけれど、まだ介護施設に入る年齢ではないと感じていました。
駅近で利便性の良いマンションに住み替えることで、これからの生活をより安心・快適に過ごせるようにしたいという想いが高まったそうです。
住み替えと同時に、浅井さんが行ったのが遺言書の作成です。
「うちは子どもが一人だから遺言書なんていらない」と考えている方も多いでしょう。
しかし、実際には子どもが相続の手続きに関わりたくないと考えているケースも少なくありません。
浅井さんも、娘さんから「不動産の売却手続きは面倒だし、時間もない」と言われたため、遺言書に「不動産を売却換金してから相続させる」という文言を入れました。
まとめ
住まいの終活は、老後の安心を支える大切な準備の一つです。
所有する不動産の管理や相続に関する整理を早めに進めることで、子どもや家族への負担を大幅に軽減できます。
住まいの終活をスムーズに進めるにあたっては、さまざまな専門家に相談することになるでしょう。
個人での手続きに不安がある場合は、相続や住まいの終活を一括でサポートしてくれる窓口の利用も効果的です。
『めーぷる』わかば鶴ヶ島店では、不動産の売却や清算型遺贈による相続の豊富な経験があります。
相談は無料で行っていますので、いつでもお気軽にご連絡ください。
